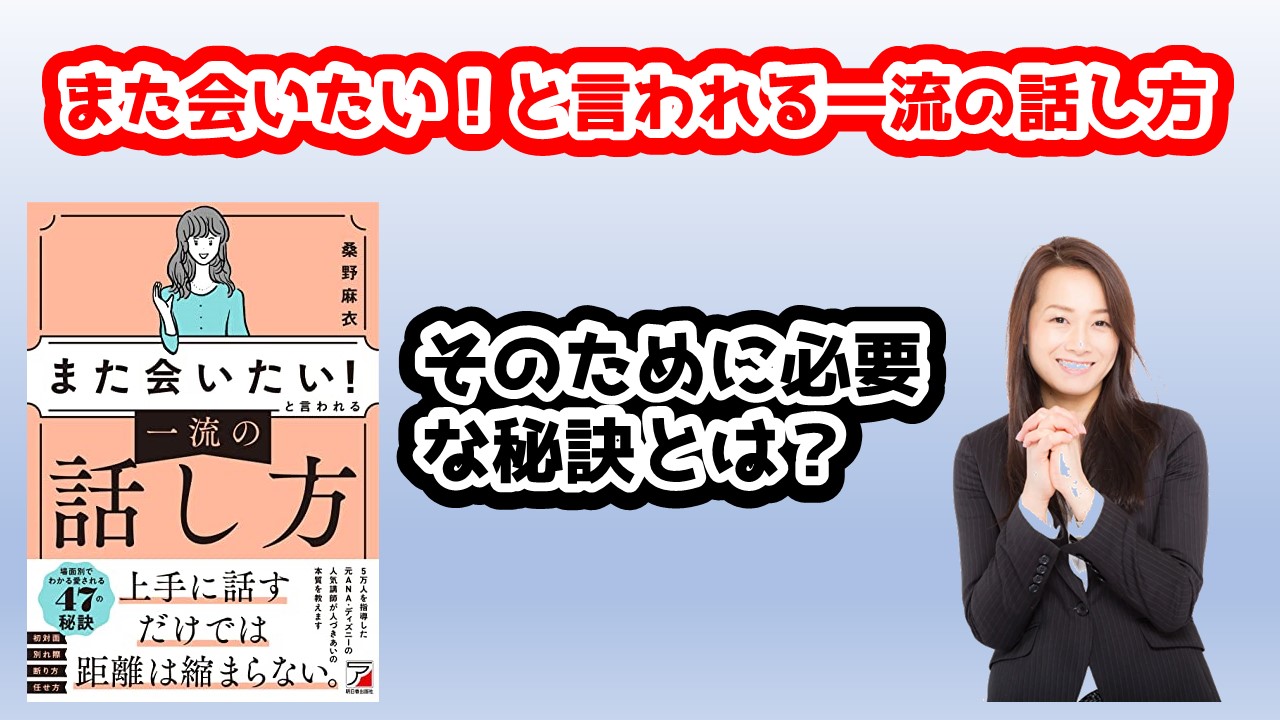今日は書籍の紹介をします。
紹介する書籍はこちら!
また会いたい!と言われる一流の話し方
桑野麻衣さんが書かれている書籍です。
著者である桑野さんは全日空、オリエンタルランド、ジャパネットたかたで勤務されたことがあります。
そこで学んだ話し方を紹介されており、桑野さんは企業研修やセミナー講師をされています。
この書では、場面別に47の秘訣が紹介されています。
私は1日で読んでしまいました。
私は元教員ですから、話すことに自信がありましたし、説明することにも自信がありました。
しかし、これを読んで私の考えは間違っていたことに気付くことが出来ました。
上手に話せている、私の説明で理解してもらえていると思っていたのです。
私はまだまだ一流ではないなと思った次第です。
そこでこの書籍で学んだことをかいつまんで説明します。
それでは行きましょう!
コミュニケーションは察することではない

まず、コミュニケーションは察することではないと書かれています。
「察する」「察してもらう」に甘え、依存してしまうとコミュニケーションはうまくいかなくなります。
所詮相手は赤の他人であり、考えていることや胸の内は表現しない限りは伝われないと書かれています。
まさにその通りです。
授業では、これで分かってもらえるだろう、これで大丈夫だろうと思っているだけではダメなんです。
理解できているのか、そうでないのかはきちんと言わなければ伝わりません。
桑野さんは、コミュニケーションとは、「心」を「形」にするものだと定義しています。
人には感情があり、相手に対して、感謝、謝罪、好意など様々な心を持ちます。
しかし、これを形にしなければ、そもそも心がないと見なされても文句が言えない。
だから察する力よりも表現する力を磨きましょう。
喜怒哀楽と言った簡単な感情表現から言葉にしてみるのがオススメです。
「好かれる」ことと「信頼される」ことの両立を目指してくださいですって。
どちらか一方ではなく、バランスよく持つことが理想です。
好きなアナウンサーランキングで思い浮かぶのが、高島彩さん、安住紳一郎さん、桝太一さん、水卜麻美さん。
アナウンススキルはもちろん、老若男女問わず愛される親しみやすさを持ち合わせています。
親しみやすさと信頼感をバランスよく持ちましょう。
自分の思いが伝わらない

自分の思いが伝わらないことってありますよね?
私も何度もあります。
そうなると、なんで分かってくれないんだよ、どうして理解できないんだよ
って相手を責めてしまう、相手のせいにしてしまう
そんなことありませんか?
桑野さん曰く、相手のせいにしていると、成長することはできないんですって。
これを読んだときにドキってしました。
そして、桑野さんはこうも言っています。
相手のせいにしている限り、あなたは話し方を磨く機会を失ってしまう上に、人として成長することはできません
もう反省だけです。
「相手の反応は自分のコミュニケーションの成果である」
あなたの中にある引き出しを増やし、伝わるまでの過程を楽しんでくださいとのことです。
アサーティブ
アサーティブという単語が出てきます。
なんだよ、アサーティブってと思いました。
一流だなと思う人は空気を読みすぎずことなく、言うべきことはきちんと言います。
だからと言って、好き勝手に言いたい放題言っている印象もありません。
この違いが3つのコミュニケーションスタイルになるそうです。
まずはアグレッシブコミュニケーション
相手に対して攻撃的な主張をするコミュニケーションタイプです。
自分がwinで相手がloseの関係です。
例えば、人から無理なお願いをされたときに、強い口調で「忙しいので無理です」とだけ言い放ってしまう人がこのタイプ。
ノンアサーティブ(パッシブ)コミュニケーション
受け身で自己主張をしないコミュニケーションタイプです。
相手はwinだけど、自分自身はloseの関係
無理なお願いをされても、「あ、はい、分かりました」と断りきれずに引き受けてしまう人がこのタイプ。
そしてこの2つの中間に位置するのがアサーティブコミュニケーションなんですって。
相手もwin、自分もwinという関係です。
無理なお願いをされたとき、まずはこう答えます・
「今は明日の午前中までに終えなければならない仕事がありますので、対応するのは難しいです」
と丁重にお断りします。その後
「明日の午後であれば対応は可能ですが、それでもよろしいですか?」
と代替案を自ら提示します。
こうなると相手のお願いを断っているのですが、マイナスになる印象は避けられます。
これがアサーティブコミュニケーションなんですって。
コミュニケーションの第一歩は傾聴すること

コミュニケーションの第一歩は、傾聴することとよく言われます。
代表的なものは、アイコンタクト、うなずき、あいづちなどが挙げられますね。
ただうなづきながら受身の姿勢ではなく、聞き手が能動的に場を作れる姿勢が求められます。
その一例として「質問スキル」があるんですって。
例えば、
「この会社で働く上で○○さんのやりがいを感じる瞬間はどんな瞬間ですか?」
「○○さんが思われる、この会社の良いところを教えていただけますか?」
と相手に聞かなければ分からない質問だそうです。
そして相手のためにも自分のためにもなる習慣があると桑原さんはおっしゃっています。
それはズバリ、「メモを取る」習慣です。
これには2つの意味があり、1つは自分の記憶として残すため、そしてもう1つは相手の言葉を大切に取り扱っていると表現するためです。
ただし、相手の顔、目を見ずにメモを取るということではなく、アイコンタクト、うなずき、あいづちといった基本傾聴を忘れずに。
メモを取ることで相手に「あなたやあなたの言葉を大切にしています」という心を形にできます。
はい、出ましたね。
コミュニケーションとは心を形にすること。
ぜひみなさんもメモを取る習慣をつけましょう。
人は自分自身に最も関心があり、自分の話を聞いてもらいたい生き物です。
初対面のときや、営業活動のとき、「自分のことを知ってもらわなきゃ、印象に残らなきゃ」と焦ってしまいますよね?
それで相手の印象に残ったとしても、「あの人は自分の話ばかりする人だったな」という印象で覚えられてしまいます。
ですので、気を付けないといけないことは、自分を覚えてもらうことを最大の目的として、相手に質問をしないことだそうです。
このことは、下心は思っている以上に相手に簡単に見破られます。
相手に関心を持ち、相手の話をよく聞き、質問することで居心地のよい空間を築けたかどうかがポイントです。
北風と太陽の話がありますね。
どちらが旅人のコートを脱がすことができるかを競い、物事へ働きかける方法の違いを表現した童話です。
太陽が勝つんですけど、重要なことは旅人が自らコートを脱いだことです。
人は誰かに無理に何かを強制される限り、積極的に行動することはありません。
つまり覚えさせようではなく、相手自らがあなたのことを「覚えたい」と思ってもらえる関係を目指しましょう。とのことなんですね。
行政書士として名刺を配ったときに、このことをまったく考えずに配っていました。
名刺を受け取ったら、質問をされるような名刺作りを心がけていましたが、相手にも質問をして、お互いいい関係を築けるよう気をつけようと思いました。
よく「思います」って言っていませんか?
みなさん、よく「思います」って言いませんか?
私も気付くと使っていることがあります。
よく会話の中でも、この人は思いますを多用する人だなって思うことがあります。
だけど、なかなか「ですます」と言い切ることって難しいですよね。
実は桑原さんも「思います」を多用していたそうです。
社内で研修講師をしていたとき、年上の受講者に対して「なになにです」と言い切れなかったそうです。
桑原さんとしては、謙虚さを表現しているつもりだったそうですが、それは完全に誤解だったと。
受講者からも上司からも語尾に「だと思います」が多いから、自信がない印象になってしまう。
プロとして堂々と言い切ってほしいと言われたそうです。
しかし、「ですます」「ません」と言い切られることに抵抗を感じる人もいることは事実です。
どのような相手にも響くメッセージを伝えられる人たちは、語尾を使い分けができています。
答えが1つしかない、正解や決められた方針があるものは「ですます」で言い切る、正解はなく、答えが複数あるもの、相手の意見を尊重したいときは「私はこう思っています」「私個人としてはこのように考えます」と語尾を和らげる。
常に相手にも選択の余地を残すことを意識しているのだそうです。
このように「私」を入れることでイメージをガラッと変えることができます。
こうすることで、語尾は柔らかいものの、曖昧さや責任逃れをしているような印象をなくすことができます。
自信がない印象にもならず、むしろ自信があり、芯の強い印象を残せるとのことです。
あなたは仕事を任せることが得意ですか?
職場に部下や後輩ができると仕事を任せる必要性が出てきますよね。
誰もが最初は仕事を任される側ですが、いざ任せる側になると苦手意識が出てくる人も多く見られます。
私も最初はそうでした。
任せるにしても、どうやって、どう言えばいいのか分からず困ったことがあります。
当然ですけど、「やっておいて」「あとはよろしくね」などと押し付けるだけでは、当然ながらやる気になってもらえません。
丸投げはよくないよなと丁寧に一通り教えた後、「分からないことがあったら遠慮なく言ってね」とフォローも大事です。
丸投げよりはよっぽどいいのですが、結局これも「やらされている仕事」には変わりありません。
教えてもらえる分、不満はそこまで抱きませんが、仕事の目的や意味は分からずじまい、結果として時間もかかってしまい、やる気も下がり、成長にも繋がりません。
相手に行動をしてもらいときは、明るい未来(メリット)を想像してもらう必要があります。
桑原さんがジャパネットたかたで働いていたとき、当時の社長である髙田明さんから学んだことがあるそうです。
ジャパネットたかたの通販番組では、その商品のスペックの説明は最小限に押さえています。
例えば、ウォーターサーバーを紹介するとき、機能や値段の説明に加え、「このウォーターサーバーがお家にあればいつでも安全で美味しい富士の天然水が飲めますよ」「定期的に自宅に水が届くから、買い物で重い水を買ってくる必要がなくなりますよ」と生活でのメリットを複数、視聴者に必ず伝えています。
このようにその商品を使うことでどのような豊かな生活が待っているのか、その便利さからどれほどの生活の変化が起こるのか伝えることを大切にしているからです。
仕事を任せて、行動を起こしてもらいたいときには、感情へのアプローチが必要です。
任せる相手に、明るい未来、メリットを想像してもらうようにしてください。
敬語の種類は覚えていますか?
みなさんは敬語の種類は覚えていますか?
丁寧語、尊敬語、謙譲語ですよね・
敬語と言えば、基本的には丁寧語を使うイメージです。
「です」「ます」「ございます」ですよね。
問題は「尊敬語」「謙譲語」です。
この2つの違いが分かりにくく、「使い分けるのが難しい」という人が多くいます。
そんな私もそうです。
実は違いは1つだけです。
相手が主語であれば、尊敬語、主語が自分や身内であれば謙譲語になります。
例えば、
言う:尊敬語ではおっしゃる、謙譲語では申す、申し上げる
聞く:尊敬語ではお聞きになる、謙譲語ではうかがう、お聞きする
言われてみればそうだ!って思いますね。
〇〇の件、知っていますか?ではなく、〇〇の件はご存知ですか?
と相手に尋ねれば丁寧な印象になります。
謙譲語を使い分けるだけで、印象に差をつけることができます。
それ聞きましたより、そちらの件はうかがいしましたと答えたほうがきちんと感が出ます。
日頃から自分の行動に対しては、自分自身をへりくだり、相手を高める表現を練習しておくと、自然と出てくるようになるとのことなので、日々練習しようと思いました。
思いましたじゃないですね。練習します。
敬語を使う理由について考えたことはありますか?
みなさんは敬語を使う理由について考えたことはありますか?
私はありません。
敬語が正しく使える人とそうでない人の違いは、実はここにも表れるそうです。
文化庁が発表している「敬語の指針」に、敬語を使う2つの理由が書かれています。
1つ目は「相互尊重」という考え方。
「敬語は、人と人との「相互尊重」の気持ちを基盤とすべきものである」と書かれています。
年齢や立場に関係なく、目の前にいる相手のことを尊重し、失礼のないように敬語を使いましょうという意味です。
2つ目は「自己表現」という考え方。
「敬語は、自らの気持ちに即して主体的に言葉遣いを選ぶ「自己表現」として使用するものである」とあります。
正しく敬語が使えることは、あなたにとって武器となり、自信にも繋がります。
桑原さんが人気な先生のセミナーに参加したとき、お話自体は納得の行くものでしたが、「なんだよねー」「うん、うん」といった語尾やあいづちが多く、残念な印象の方が強く残ってしまったそうです。
「人柄はいいんだけど、自分の大切な人に紹介するには抵抗があるなー」と思う人の共通点として、敬語を正しく使えないことがよく挙げられます。
敬語が使えないことで、相手を軽んじているように見えることが理由だそうです。
また、「敬語すらできないということは、違う部分でも気を使えないのでは?」と思われかねません。
敬語の持つ影響力を理解できている人は、たかが敬語なんてとは絶対に言いません。
相手に対して失礼である以上に、相手の価値も下げてしまう危険性を理解できているからです。
一流の人たちは相手を尊重し、自分を正しく表現するものとして、敬語を学び使っています。
敬語が使えるだけで、自分の価値を上げられるそうです。
話のプロ

話が上手な人はたくさんいますが、誰もが思わず聞き入ってしまうほどの話のプロにはなかなか出会えないとおっしゃています。
その違いは「間」の取り方だそうです。
沈黙を怖がって無理やり話し続けていては、適切な間を取ることはできません。
そもそも間は何のために存在するのでしょうか?
実は、間は目の前にいる聞き手のための時間なのです。
桑原さんが出会った中で最も間の取り方が素晴らしかったのは、ジャパネットたかたの髙田明さんだそうです。
間術師と言われるほど、間を意識して商品紹介をされていたそうです。
実際に通販番組で商品紹介をするとき、金額を言う前に2から3秒の間があるかないかで、売れ行きに大きな差がついたそうです。
間術師になるための3つの「間」が紹介されています。
①強調
ここは覚えてもらいたいと相手に強調したい内容の直前に作る間です。
学校の先生が言っていた「今から話すことをよく聞いてください。(間)今度のテスト範囲を説明します」
最も相手の印象に残りやすい間の取り方かもしれません。
私もよく使っていました。
②問いかけ
この間は、相手に考えてもらうための時間として作ります。
これもよく使っていました。
みなさん、これについてどう思いますか?
と問いかけて間を作るやつです。
最も取り入れやすく、会話のボールが分かりやすく、相手に渡るので、沈黙に耐えられないという状況にはなりません。
③整理
この間は相手に頭の中を整理してもらうための間です。
面接でもよくありますね。
ここまでの内容で質問はありますか?
ご不明な点やご質問はありますか?
というやつです。
一度立ち止まってもらいたいときに入れます。
話し手は暑くなるとつい一方的に話してしまいがちなので、あらかじめこの③整理の間を組み込んでおくことを桑原さんはオススメしています。
まとめ
いかがでしょうか?
この本を読んで、今まで自己流で、好きなように話していたことが分かりました。
また、敬語ですよね。
これの重要性が分かったかと思います。
この本はサラリーマンのみならず、講師や自営業の人も読んで損はない内容です。
最後にリンクを貼っておきますので、ぜひ買って読んでみてください。
それではまた!